Contents
しないDXとは?言葉の意味をおさらい
DXの正確な意味
DXと言葉が広く使われるようになりましたが、その意味を正しく理解できていない人も多いです。
これからビジネスで実現することを視野に入れているなら、正確に理解しておく必要があります。
これはデジタルトランスフォーメーションの略であり、アルファベットを省略せずに表現すると「Digital Transformation」です。
デジタルの歴史全体から見ると比較的新しい言葉であり、誕生したのは2004年となっています。
スウェーデンにある大学の教授が提唱し、それが少しずつ形を変えながら広まっていきました。
本来の意味は、テクノロジーが発展し続けて人々の暮らしを豊かにするというものです。
このテクノロジーが指すものはデジタル分野の技術で、その浸透が生活のレベルアップには欠かせません。
レベルアップの主体はあくまでも生活の水準ですが、ビジネスシーンもデジタル技術が活用される主な場面の一つです。
その成果が人々の暮らしにも及ぶと考えると分かりやすいでしょう。

前述のアルファベットを直訳すると、デジタル変換になると指摘する人もいます。
デジタル変換と聞いて理系の人がイメージしやすいのでは、連続値を離散値に置き換えることです。
たしかにこの作業はデジタル変換と呼べるものですが、DXにおける概念とは大きく離れています。
なぜなら、DXにおける変換とは変革を意味するものだからです。
アナログをデジタルに直すような具体的な概念ではない点に注意してください。
そうしないと、コンバーターなどの装置と勘違いしてしまう恐れもあります。
また、変革という表現も適切に認識しなければなりません。
単純な置き換えとは違い、革新と呼べる大規模な変更をもたらすものです。
既存の考え方や価値観をすべて打ち払うような強烈なものを指しています。
近年いろいろな業界でイノベーションという表現がよく使われるようになりました。
これも根底から覆すような大きな変化を指しますが、それと同じように認識しておくと良いでしょう。
技術が進化するだけではDXとは言えない
デジタル技術の浸透を人々の暮らしの向上に結び付けて考えることが大切です。
単にデジタル技術が進化するだけではDXとは言えません。
それは技術の進歩に過ぎず、あくまでも技術分野における成果になります。
そうではなく、最終的に生活のクオリティに帰結することが不可欠です。

そのためには、従来から定着している価値観を取り払えるだけのインパクトが求められます。
枠組み自体を消し去るような変革がなければ、DXを達成したことにはなりません。
あくまでも言葉の意味に関する話に過ぎませんが、これからの時代において不可避ともいえる概念です。
日常生活で使われるレベルには至っていませんが、まだ認識していないだけで、すでに身の回りで起こりつつあります。
そう聞かされると、インターネットの高速化やSNSの普及を思い浮かべる人もいるでしょう。
それらはIT化の延長にあるものであり、DXとは異なるので気を付けなければなりません。
IT化と混同している
抽象的な要素が多い言葉なだけに、IT化と混同しているケースが多く見受けられます。
IT化を包括している概念であり、同次元のものではない点に注意が必要です。
DXに明確な定義が存在しないことも、この勘違いを助長させる要因となっています。
分かりにくければ、IT化はDXを達成する手段の一つと捉えましょう。
最も大きな手段であるのは間違いありませんが、それだけで成し得るものではありません。
そう言われると、DXのほうが立場が上だと感じる人もいるでしょう。
両者の間に上下関係は存在しないので誤解しないでください。
IT化の目的が必ずしもDXではないこともポイントの一つです。
単純にこれまでの作業を簡略するために実施した場合は、それは変革と呼べる作業ではありません。
したがって、IT化ではあってもDX化ではないということになります。
別の見方をすると、IT化は量に注目して実施されることが多いです。
それに対してDXは、あくまでも質の向上を目指して行われています。
国が発表したガイドライン
国はDXのガイドラインを発表していますが、それはあくまでも推進を後押しするものに過ぎません。
技術的な観点でその定義が正しいとは言い切れないですが、現状としては最も信憑性があります。
ただし、後述するように経済産業省はビジネスシーンを想定して定義しています。
したがって、これを一般的なDXに落とし込んで考えるしかありません。

そうすると、デジタル技術を活用しながら暮らしやすい社会を実現していくという意味になります。
ここでの暮らしやすさにも明確な定義は存在しておらず、風土や文化も考慮した生活のクオリティということになるでしょう。
IT化は局所的な効果に留まることが多いですが、DXが成功した場合は社会に向けて大きな変化を発信します。
その前には分かりやすい目的が定められており、それを実現する手段として実施されるのが一般的です。
ビジネスシーン以外でのDX
日本におけるDXはビジネス用語として広がっており、これから使用するシーンも職場などに限られるのが実情です。
しかし、本来の意味を把握していないと、正しく言葉を使えないリスクが高まります。
ビジネスシーン以外でも、着実にDXは起こるようになってきました。
その形はこれからも変容していくと予想されますが、生活のクオリティ向上には欠かせないことを理解しておきましょう。

変容をもたらすものがデジタル技術であることは確かですが、その背景には人のクリエイティブな発想が存在します。
そのような発想のなかには、以前から存在するものも多いはずです。
しかし、具体的な形にするだけのテクノロジーが整っていませんでした。
急激なIT化によって、それらを実現できるステップにまで辿り着いたと解釈できます。
もちろん、まだ実現できておらず、アイデア止まりになっているケースも珍しくありません。
このように、これだけIT化が進んでいても、概念自体に時代が追い付いてきたばかりの状況です。
したがって、言葉のニュアンスは固定されていませんし、これから変化していく可能性も高いです。
それを頭の片隅に置いたうえで、DXという言葉を誤解のないように使っていくと良いでしょう。
ビジネスシーンにおけるDXの定義
自社のビジネスモデルを変容させていく
DXの言葉の意味は上記のとおりですが、ビジネスシーンに限定すると微妙に変わってきます。
経済産業省のガイドラインが有力な拠り所になるので、まずはそちらを理解しておくことが大事です。
IT系のサイトなどに独自の解釈が書かれていることも多く、そちらのほうが実情に対して妥当性があるケースも見受けられます。
しかし、公式な場面でDXの説明をする場合、優先されるのはやはり国が打ち出した文章ということになります。
ビジネスシーンの激しい移り変わりにのいて、企業がデジタル技術とデータを活かすことは欠かせません。
顧客のニーズを理解することが重要であり、社会全体で求められているものも把握する必要があります。
それらの情報をベースとして、自社のビジネスモデルを変容させていくスタンスが大事です。
商品やサービスの改善だけでなく、業務や組織を見直すことも含まれています。
適切なプロセスを明確にしたうえで、企業風土や企業文化にもイノベーションを起こします。
そうして、他社との争いにおいて優位性を確保することが大きな目的です。
ビジネスの影響があるもの全体に変化を及ぼす
上記が公式の大まかな解釈ですが、要するにデジタル技術やデータをビジネスで活用することが基盤となっています。
それだけでは不十分であり、ビジネスの影響があるもの全体に変化を及ぼすという意味です。
高度なデジタル技術があれば、これまで不可能だと思っていた商品を実現できることもあるでしょう。
サービスにしても同様ですが、単発でリリースするだけでなく、ビジネスモデルとして確立することが条件となっています。
さらに、工程を再構築することなども入っており、既存の業務や生産性を改善することも対象です。
もちろんコストや手間の削減も例外ではなく、ビジネス全般を抜本的に改変していくことが含まれています。

ここまで聞いて、働き方改革をイメージする人もいるでしょう。
そちらの実現についても重要な役割を果たしており、テレワークがこれだけ普及したことにもDXは大いに貢献しています。
すなわち、DXは社会の在り方も大きくステップアップさせうるものです。
IT機器の導入
ビジネスシーンでは、最新のIT機器を導入するケースは少なくありません。
まず大学などの研究機関で基礎技術が生まれ、それが企業の研究所などで試作品という形になります。
そして、製造部門で量産化されて市場に出回りますが、それらを最初に購入するのは企業です。
量産化されたばかりの頃は、まだ価格が高い一方で知名度はそれほど高くありません。
VRの装置をイメージすると上記の例は分かりやすいでしょう。

仮想体験ができる仕組みは、まずアミューズメント施設に高価なものが導入されました。
それがVRという概念を世間に広める役も務めることになります。
それから数年の時を経て、一般家庭のゲーム機でも使用できるものが発売されました。
また、一般家庭ではゲームにおける使用に留まっていますが、ビジネスの分野ではもっと広く活用されています。
建築業界では、仮想空間にモデルハウスを建てることが一般的になってきました。
実際に建てるよりもはるかにコストが安く、すぐに手直しできるというメリットも大きいです。
顧客と相談しながら、要望をリアルタイムで反映させることも難しくありません。
日照条件などを変えて、シミュレーションを実施することも容易です。
また、近年になって脚光を浴びているIoTと連携させるケースも増えてきました。
離島で暮らす子どもたちに、都会の学校の授業を受けさせることなどが有名な事例です。
テレビのCMで大々的に放映されていたので、ずいぶん前から知っている人もいるでしょう。
パンデミックが起こった際に、VRでイベントを実施する事例も多く見られました。
それの発展形として、旅行を仮想空間で楽しめるようなサービスも提供されています。
仮想空間で会議を実施するシステムも登場するなど、ビジネスの世界と深い関連性を持っているのが実情です。
これはあくまでもVRに限定した話ですが、それ以外の分野でも同様の変化が起こっています。
いずれに関しても、上記の定義に当てはまっており、最終的には生活の質を向上させることにつながっているのです。
DXかどうかを判断できない場合
自社における変化がDXかどうか判断できない場合もあるでしょう。
そのようなケースでは、DXを取り除いたらどのように状況が逆行するのが考えてください。
もしビジネスにおける勝敗に変化が生じないなら、それは単なるIT化である可能性が高いです。
ビジネスモデルをチェックすることも重要な手がかりになるでしょう。
取り除いてもビジネスモデルが変わらないなら、その事象はDXとは呼べません。
ビジネスの根底にあるものを大きく変容させることが重要な定義であると理解しましょう。

ただし、前述のように明確な定義があるわけではありません。
そのため、自社がDXでないと判断した変化であっても、他社はDXに該当すると判断するケースもあります。
どちらが正しいか知りたければ、経済産業省のガイドラインに照らし合わせて、しっかりと検証するしかありません。
アナログだったプロセスのすべてをデジタル化した場合は、DXに当てはまることが多いでしょう。
アカデミックな言葉として使われ始めたDXも、今や立派なビジネス用語として名を連ねています。
そのため、早期に把握しておくことは、ビジネスマンの教養としても大事なポイントです。
デジタル時代が進むにつれ、勝ち残るためのノウハウも変わってきました。
その競争力の研磨を欠かさず、自社に革新をもたらしていくことが基本的な意味合いです。
漠然とした部分も多くありますが、たいていのビジネスシーンではそのような概念で使用されています。
誤解を招かないようにするには、一部のプロセスにのみ影響を及ぼす変化を除外することが欠かせません。
他社のDXとして挙げられている事例をチェックすれば、自社がその定義に当てはまるか判断しやすくなるでしょう。
長いスパンで事業を見られる視野を持ち、そのうえで変化を生じ続けさせるという解釈も可能です。
一朝一夕で起こりうる事象ではないので、とにかく単発の変化ではない点に注意しなければなりません。
なぜ今、DXが注目されているのか?
これまでのビジネスが通用しない世の中になったから?
DXが急激に注目を集め始めたことには大きな理由があります。
その背景にあるのは、これまでのビジネスが通用しない世の中になってきたことです。
収益が鉄板と考えられていた業界でも、今や風前の灯火となっているケースが少なくありません。
デジタル技術が加速度的に発展したことで、製品やサービスの在り方に多くの変化が生じることになりました。
以前から高度なデジタル技術は存在しましたが、それらは一部の先進的な企業に牛耳られていたのが実情です。
その時代が終わりをつげ、新興勢力がさまざまな分野で台頭してきました。
そのなかには、従来の常識を払拭するようなビジネスモデルを展開する企業も多く見受けられます。
続々と現れており、今後もその勢いが弱まることはないでしょう。

このような風潮が続く中、先行している企業も手をこまねいているだけではありません。
自分たちが持っていたシェアを奪われないように、早い段階から手を打っているケースも多いです。
その手段の筆頭になっているのがDXであり、競争力をキープしながら強みを生み出すことに力を入れています。
DXを進めるには、ある程度のコストがかかることも避けられません。
実施が可能な企業は歴史の長い企業が中心?
たとえば、インターネットすら導入していないなら、大規模な工事が必要になる可能性もあります。
IT化の具合によっては、パソコンを大量に購入するような状況になることもあるのです。
起業したばかりの会社には、それだけの経済力が備わっていないことも多いでしょう。
ですから、必然的に実施が可能な企業は歴史の長い企業が中心となってきます。
それらの企業が新規参入組への対抗策として遂行するケースが目立ちます。
収益が得られる分野で、独占状態を維持するのは容易ではありません。
以前と違って新規参入組は、入念な施策を講じたうえで挑戦してくるからです。
情報ビジネスが盛んになっており、もはや手に入らないノウハウは皆無といっても良いでしょう。
自分たちのアドバンテージがあると考えると、その驕りが命取りになるので注意してください。
そもそもDX化が必要ないほど、デジタル技術を最初から活用している企業も多く見受けられます。
古い体質の企業は、なす術もなくシェアを奪われかねません。
自分たちがスタンダードという思い込みを捨て去ることが重要です。
2025年問題
たとえば、SNSの活用方法を知らない企業は、それを熟知している新興勢力に追い抜かれるリスクがあります。
太刀打ちするには、プロモーションの仕組みにSNSを導入することが大事です。
とはいえ、企業に染みついた既存の方法を捨てて、一から組み直すのは容易ではありません。
そのため、本格的にDXを推進しているのは、一部の部門や組織に限られているのが実情です。
必要性は理解できても、着手できないという状況が普通になっています。
先進的な部門などが挑戦し、それが成功したこと見届けることが既定路線です。
そして、成功の確証を得たうえで、手順を踏襲することが一般的となっています。
前述の経済産業省のガイドラインも、この現状に起因するものです。
デジタル分野において先進国と比べて遅れていることに危機感を持ち、国内の企業を導くために発表したという経緯があります。
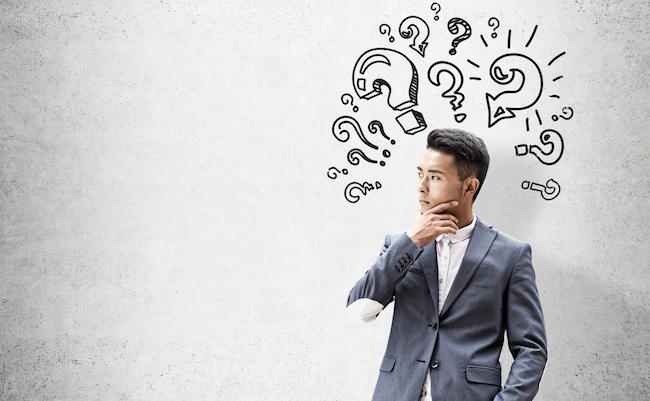
また、既存のシステムの老朽化が顕著になり始めるタイミングだったことも関係しています。
ここで多くの企業が没落すると、デジタル市場を活性化させることは不可能です。
そのようなリスクを最小化して、ビジネスシーンのメインフレームを整えていくためにも、経済産業省のガイドラインは必要なものでした。
労働者の高齢化もシステムの置き換えに影響しますし、少子化による働き手不足の解消も欠かせません。
こういった問題を解消するための手法として、DXは必須といえるものです。
2025年にはこれらの問題が顕著化すると考えられており、それまでにDX化を達成することが理想となっています。
もちろん、達成できない企業が続出するケースも想定済みです。
そのような企業は市場の変化に追従できず、陳腐化したビジネスモデルに依存し続けることになるでしょう。
つまり、デジタル市場において明確な歯医者になるというわけです。
そこから立て直すことは用意ではなく、多くの企業が倒産に追い込まれるのは間違いありません。
それは日本経済に深刻なダメージを与えると見られるため、国はガイドラインまで出して注意を喚起しています。
旧式のシステムを維持できなくなることも懸念される点です。
システムを扱える技術者が減るにつれて、維持費や管理費は高騰していきます。
これは技術的な負債に該当し、業務の基盤を継承すること自体も困難です。
さらに、セキュリティ面において脆弱な状態になり、顧客データの流出などのリスクが高まります。
クラッキングの技術は年々高度化しており、ウイルスの種類も爆発的に増えているのが実情です。
DXが不完全な状態だと、それらの攻撃をまとめに受けることになるでしょう。
その結果、回復できないほどのトラブルに見舞われ、やはり倒産の危機を迎えてしまいます。
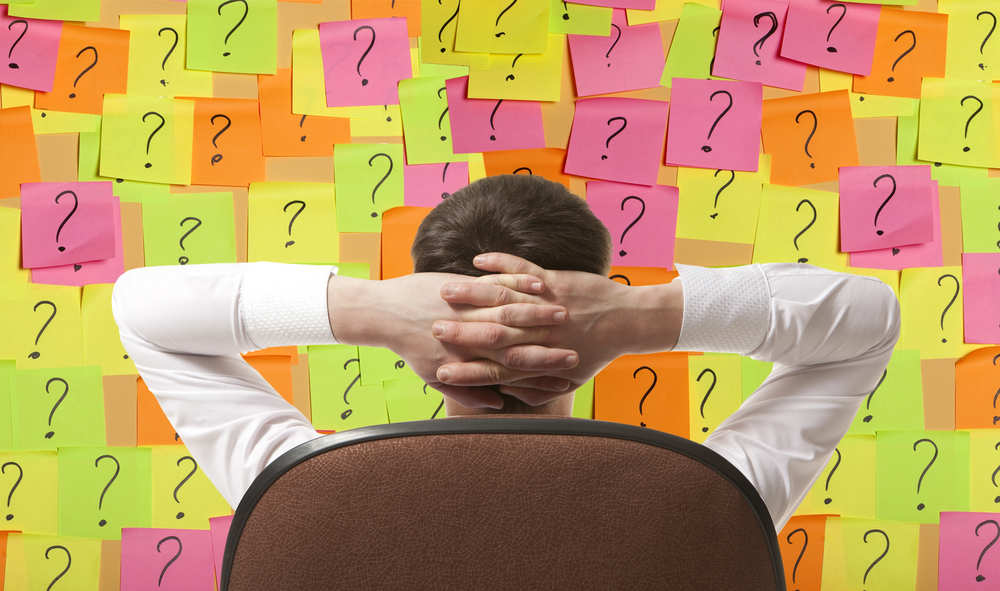
このように多角的な脅威に包囲されており、遅かれ早かれ経営は危機的な状況を迎えやすいです。
以前からこの予測はされていましたが、経営者の間で楽観的な風潮が強くありました。
2025年が目前に迫ってきたことで、現実の懸念材料として捉える企業が多くなったのです。
また、従業員の入れ替わりが進んでいることも影響しています。
IT技術に長けた若い世代が入社し、DXと無縁な現状に関して問題を提起するパターンです。
新入社員の頃は意見を聞いてもらえませんが、ある程度の出世により主張を受け入れてもらえます。
多くの企業でそのタイミングが訪れており、古い価値観を持つ経営層の間にも、本腰を入れて取り掛かる気運が高まってきました。
つまり、DXが注目を集めるようになったのは、リスク対策の重要性が明らかになったからです。
このまま放置していると、数年後にはシェアを奪われ、最悪の場合は倒産に至るでしょう。
これを回避するために取り得る措置として、DXが国から推奨されています。それを知った経営層がDXに着目するのは自然な流れです。
DXの推進にむけた企業の現状と課題
企業がDXを推進する方法には複数のパターンがあります。
そのなかでも中心となるのは、最先端のデジタル技術を積極的に挿入するというものです。
特定の工程を改善するだけなら、あえて最新のものを使う必要はないでしょう。
しかし、DXはそのようなスケールではなく、経営戦略を根本的に変えるような影響力を持つものです。
ビジネスモデルを変容させることが前提であり、経営戦略の一部として組み込まれなければなりません。
このような事例は他になく、多くの経営者に戸惑いの色が見られます。
DXが大切なのは周知の事実ですが、経営戦略に挙げるほどのものなのか判断しかねます。
特に年配の経営層は懐疑的であり、二の足を踏んでいるケースが多いという実情です。
つまり、認識と現実の間に齟齬が生じるような状況になっています。
若手社員の流出問題
こうして具体的な施策を打ち出せないまま、問題の本質に近づけていない企業が少なくありません。
はっきりとしたビジョンがないので、無駄な討論を繰り返すような事態になっているのです。
たとえば、AIを使いたいという漠然とした考えがあっても、そのアプリケーションのアイデアはありません。
アプリケーションの開発にも疎いため、前進が見られない状況が続いているというわけです。
このような事例が多く報告されており、早くも国全体のDXは暗礁に乗り上げています。
若手が必死に意見を突き上げても、経営層に却下されることもよくあるパターンです。
そのため、最大の課題として、経営層の理解不足を挙げる人も珍しくありません。
既存のシステムのデメリットを列挙しても、新システムに対する苦手意識が勝ってしまいます。
若手と違って、年配者は自分の考えを簡単には変えようとしません。
自分が定年退職を迎えるまで、システムを変えることは避けたいという人もいます。
もはや自分のことだけを考えおり、企業の将来から目を反らしているのが実情です。
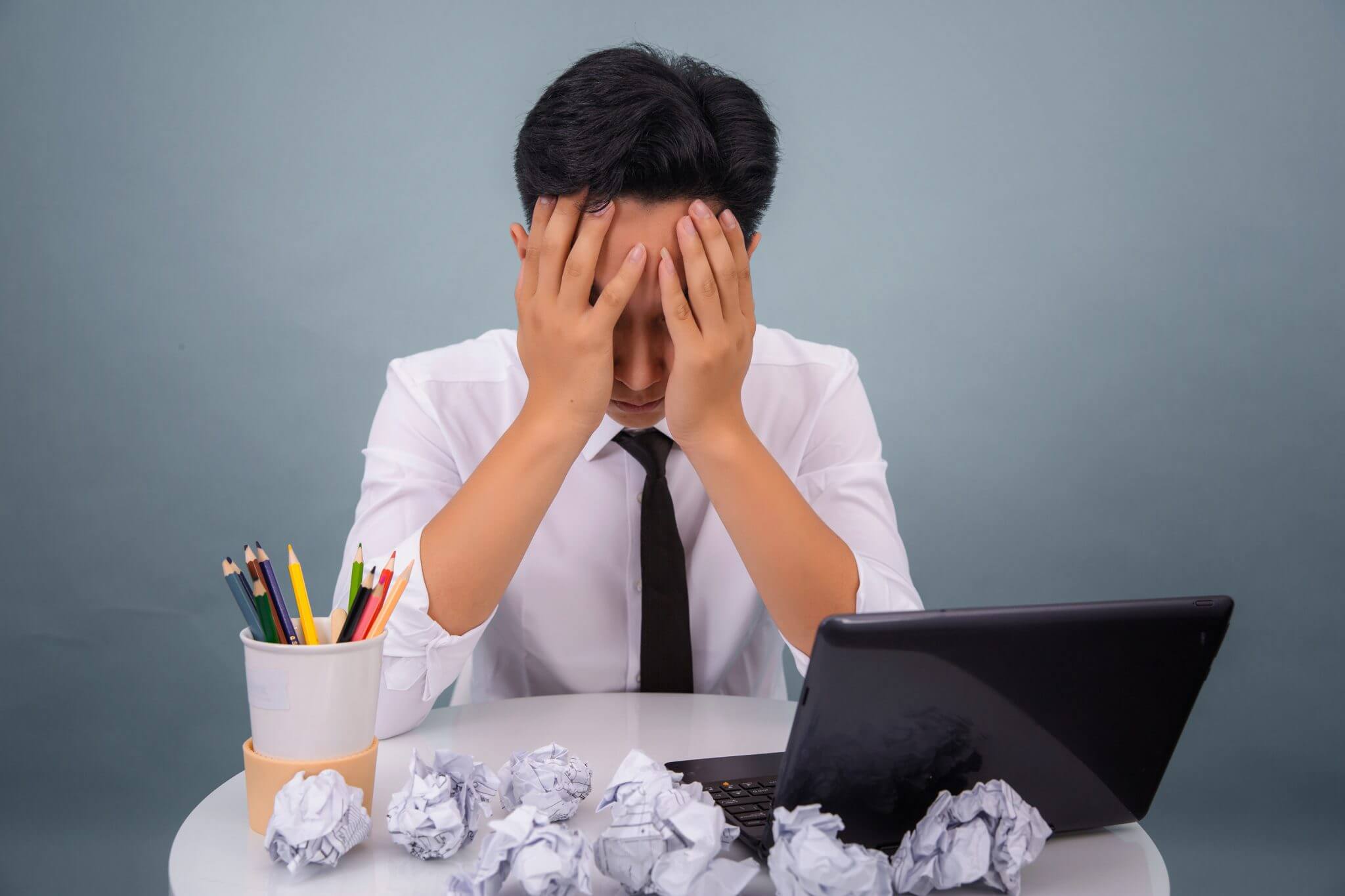
そのような従業員が多くを占めていると、DXが進まないことも当然といえます。
今後をしっかり見渡して、自社のビジネスモデルを変革しようとする気概が欠かせません。
経営層に一人でもそのような人物がいれば望みがありますが、たいていの場合は同類の年配者が顔を連ねています。
若手社員が中心となっているベンチャー企業に、自分たちが負けてしまう将来を現実のものとして考えられません。
このような企業で次に起こるのは若手社員の流出です。
ITを含むデジタル分野に詳しい従業員ほど、自社が泥船にように見えることでしょう。
一向にDXが進まない状況に落胆し、逃げ出そうとするのは健全な防衛本能によるものです。
最初は必死に経営層に働きかけても、暖簾に腕押しの状態が続くと諦めざるをえません。
若手社員が抜けてしまうと、DXの推進を求める声が一段と弱くなります。
このような負のループが生じ、DXの失敗というルートに入り込んでしまいます。
一刻も早く着手しなければならない企業も多いですが、そういうところほど危機感が欠如しているのです。
自分がDX化を推進する立場なら、経営層をしっかり巻き込む風潮を作らなければなりません。
どのようなリスクが待っているのか解説するだけでは、経営層の心を動かなせない可能性が高いです。
なぜなら、自分たちの成功体験に自信を持っており、失敗することをリアルにイメージできないからです。
そこでポイントになるのは、DXがもたらす恩恵をしっかり説明することです。
それが収益につながることを察知すれば、魅力的なプロジェクトとして受け入れてもらえる可能性があります。
ロードマップを具体的に提示し、うまく経営層の興味を引けたら、実施しない場合のリスクについても教えると良いでしょう。
メリットとリスクの落差が効果的に作用し、導入を支持する声が集まりやすくなります。
デジタル分野の人材確保
このようにほとんどの企業では、技術面よりも考え方に問題があります。
ただし、技術面に関して油断できる状況でないことも確かです。
デジタル分野に強い従業員がいなければ、DXが推進される環境を作り出せないからです。
その場合はコンサルタントなどに依頼する必要があり、通常よりも多額のコストが発生してしまいます。
経営層にそれを述べると、さらにDXを認めてくれる可能性は低くなるでしょう。
この課題を解決にするには、デジタル分野に詳しい従業員を確保することが先決です。
そのような人材を採用するという手もありますし、社内で教育するという方法もあります。
いずれにしても費用がかかりますが、コンサルタントを利用する場合と違いは大きいです。
こちらに関しては、今後のDXを支え続ける人材として、継続的な活躍を期待できます。

ただし、人材を育成する方法を選ぶならできるだけ早期に着手しなければなりません。
情報処理の資格を取得することも視野に入れ、少なくとも1年は猶予を見ておく必要があります。
それほど長く待てないなら、中途採用で人材を確保するのが一般的です。
ネットワーク関連やデータベース関連の有資格者など、優れたノウハウを持つ人材を雇用することになります。
教育した場合と比べて、人件費は継続的に発生する点に気を付けてください。
予算の再計算も必須になり、下手をするとDXのコストが著しく高まりかねません。
一人だけで対処できるものではないため、たいていの場合は数人を採用することになるでしょう。
かなりの出費が見込まれるので、教育を選んだがほうが良いケースも多いです。
企業の現状をしっかり認識したうえで、課題の対処方法を検討する必要があります。
上記の課題はどれも代表的なものですが、それらを完全にクリアできている企業は決して多くありません。
特に問題が長期化しやすいのでは、経営層の拒否が大きなネックとなって困っているケースです。
自分だけで訴えても進展がないなら、そもそも経営層が自分を信頼していない可能性があります。
その場合は、経営層から信頼を得ている先輩などに相談しましょう。
それだけでなく、できるだけ多くの人にDXの必要性を説くことも忘れてはいけません。
そうして賛同をたくさん集めることが、DXの推進を実現するための糸口になるからです。
DXの推進に必要な“DX人材”とは?
DXを推進する人材には、そのために必要な素養が求められます。
前述のようにデジタル分野に長けていることはもちろんですが、ビジネスシーンにおいてはその素養だけでは足りません。
DXのコンセプトをしっかり理解したうえで、リーダーシップを発揮できることも条件になります。
なぜなら、DXは決して一人で達成できるものではないからです。
企業の規模にもよりますが、数十人のチームで挑むようなケースもよくあります。
支社があるような大企業なら、空間的に離れている部門とのやり取りも発生しやすいです。
また、多かれ少なかれすべての従業員が作業をすることになるでしょう。
必要とされるのはスピード感のある人材
たとえば、自分のパソコンにツールをインストールするような作業が発生します。
そのため、多くの人たちを先導できるような人柄であることも、必須といえる特徴の一つです。
適切なスケジュールを組める冷静な判断力も不可欠となります。
DXは慎重に実施することが重要ですが、あまり悠長に取り組むことも考えものです。
遂行中も事業が続いていることを念頭に置きましょう。
デジタル機器の種類にもよりますが、現状のものを停止させないと置き換えられないこともよくあります。
その間は業務がストップするような事態も起こりえますし、復旧までに時間がかかるトラブルが起こるかもしれません。
そのようなリスクを踏まえたうえで、短期間で済ませることが理想的です。
継続的に更新していくものですが、最初の大きな一手は1カ月ほどを目安に完結させましょう。
それが行えるようなスピード感のある人材が必要です。

なお、デジタル分野は移り変わりのペースが尋常ではありません。
そのため、DXを推進している途中も、常に知識をアップデートしていくことが求められます。
たとえば標準的な通信規格が、完成までに陳腐化するような可能性も十分にあります。
したがって、貪欲に学習する意欲を持っていることも条件となっています。
既存の知識だけで対処しようとすると、その知識を得た時点でしか完成させられないシステムになるでしょう。
推進する人物を選定する役目の人は、どのようなスキルが必要なのか知っておく必要があります。
その基準を満たす人物をピックアップし、ヒアリングを通じて採取的に決定するのが一般的です。
もちろん、データの活用に長けていることや業務に広く精通していることも欠かせません。
デジタル技術によって何が可能か見極めるための嗅覚も大事です。
全体を統括するプロデューサー
複数の人材に任せる場合は、早い段階で役割分担を明確にしておきましょう。
全体を統括するプロデューサーを最初に決めるのがセオリーです。
前述の計画などは基本的にプロデューサーの仕事であり、自社のビジョンなども熟知していなければなりません。
既存のシステムも十分に理解して、その問題点を抽出できる視野の広さも求められます。
責任が重大なポジションであるため、一般的に任命されるのは、管理職やチームリーダーといった立場の人たちです。
課題を設定するスキルを持っており、目標に向かって行動に移せるタイプは向いています。
複数の組織にまたがって活動することも多いため、折衝や交渉といったマネジメント力も大切です。

一方、計画の立案役としてプランナーを設ける場合もあります。
プロデューサーには管理と統括に専念してもらい、全体をスムーズに進めやすくするためです。
プランナーはビジョンをもとに企画し、ビジネスの方向性を把握していることが必須となります。
DXの要であるビジネスモデルの創出にも関係する重要な条件です。
たとえDXが成功したとしても、他社より顕著に遅れていては敗北しやすくなります。
そのような事態にならないようにするプランニングもポイントです。
さらに、合意の形成を促すようなサポート役も任されることがよくあります。
DXの潤滑油として、巧みに立ち回れるだけの器用さが必要です。
裏方的な存在ですが、全体的に及ぼす影響は小さくありません。
システムの設計者
システムの設計者もDXの進展に大きく関係します。
プロデューサーやプランナーの案を具体的な形にすることが仕事です。
SEが努めることも多く、仕様を決定するために要件の定義から始めます。
デジタル分野の素養が深く求められますし、ソリューションを提案できるだけのITスキルも不可欠です。
一方、データ分析を得意としている人物も中枢を担うことになるでしょう。
DXというとデジタル技術を意識しがちですが、その背景にある目的を見失ってはいけません。
たいていの場合はデータの活用が前提となっていますし、ビックデータを活用するようなケースも目立ちます。
したがって、分析の技術が秀でていないと、相応のシステムを用意できないリスクがあるのです。
もちろん、システムの実装にはデザイナーやプログラマーが果たす役割も大きいです。
いくら高性能なシステムでも使いにくければ評価は半減してしまいます。
直感的に使用できるインタフェースをデザインすることはとても重要です。
効果的な実行できるように、適切なソースコードを書けることも条件になります。
この2つの役割を一人で担当するケースも多いですが、人材に余裕があるなら分けると良いでしょう。
インタフェースに関しては、プランナーなどの意見を取り入れることも有効です。
そうしてプロトタイプが完成したら、何度もテストを繰り返してエラーを洗い出します。
以上のように、DXの推進に必要な人材は多岐にわたります。
そのような人物がいないなら、前述のように教育や採用を視野に入れましょう。

ただし、段階的にDXを実施していくという対処法もあります。
そうすれば、少ない人材でも最終的に達成できる可能性が高いです。
進捗に合わせて、不足している知識を補充していけば、新たな人材を確保するコストも節約できます。
また、見落とされがちですが、好奇心が旺盛であることも重要な素養です。
新しいことに強い関心を寄せる人のほうが適しています。
なぜなら、DXの先に待ってきるものは自社にとって未知の領域だからです。
試行錯誤を繰り返すことになるため、飽きやすい性格の人には向いていません。
好奇心を原動力として、成功を目指してチャレンジを続けられる人材が重宝されます。

- 「しちてんはっき」何度転んでも挫けずに起き上がる。焦らないで!自分らしく! 自分のペースでチャンスを掴め!!
最新記事
 営業メール・メルマガ2024年3月24日オプトインとは?メールマーケティングでの利用法と信頼関係構築のポイント解説
営業メール・メルマガ2024年3月24日オプトインとは?メールマーケティングでの利用法と信頼関係構築のポイント解説 商談・営業手法2024年3月21日ビジネス成功の鍵!リテンションとは何か?その意味と企業における重要性解説
商談・営業手法2024年3月21日ビジネス成功の鍵!リテンションとは何か?その意味と企業における重要性解説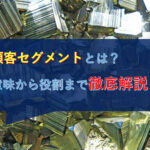 顧客・見込み管理2024年3月15日顧客セグメントとは?意味から役割まで徹底解説!
顧客・見込み管理2024年3月15日顧客セグメントとは?意味から役割まで徹底解説!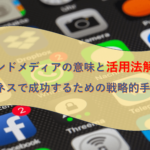 集客・マーケティング2024年3月12日アーンドメディアの意味と活用法解説!ビジネスで成功するための戦略的手法
集客・マーケティング2024年3月12日アーンドメディアの意味と活用法解説!ビジネスで成功するための戦略的手法








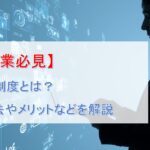




 PAGE TOP
PAGE TOP